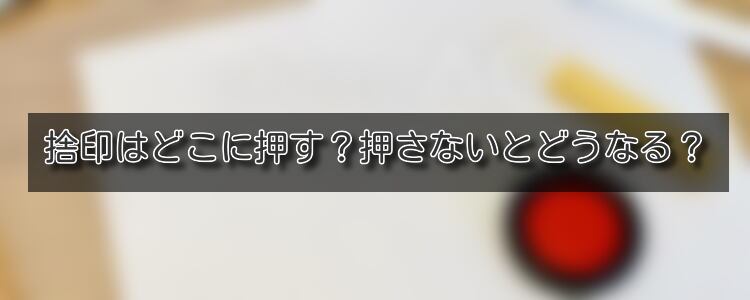
契約書や申請書など、大切な書類にときどき登場する「捨印(すていん)」。
何気なく押しているけれど、「捨印ってそもそも何?どこに押すのが正解?押さないとどうなるの?」と疑問に感じたことはありませんか?
この記事では、捨印はどこに押すべきなのか、押さないとどんな影響があるのかをわかりやすく解説します。
正しい知識を身につけることで、不必要なトラブルを未然に防ぐことができますよ。
ぜひ、契約書を取り交わす前にチェックしておきましょう。
①軽微な訂正を想定した印鑑の使い方
②捨印の正しい位置と押し方の基本
③複数ページある場合や複数人で署名する場合の対応
④押さない場合やリスクへの注意点
捨印はどこに押す?
・捨印はどこに押すのが正しい?
・契約書が複数ページある場合は?
・使用する印鑑の種類は?
・複数人で署名する契約書の場合
捨印とは?簡単に言うと「事前の訂正の承諾」
捨印とは、契約書などの文書に後から軽微な訂正が発生した場合に、それを許可する目的で事前に押しておく印鑑のことです。たとえば、誤字脱字の修正や住所の数字の訂正といった、契約内容に大きな影響を与えないような箇所の変更がこれに該当します。
つまり、捨印を押すことで、後日に相手方が軽微な修正を加える場合、その変更について同意したとみなされるのです。
捨印はどこに押すのが正しい?
① 捨印欄がある場合:そこに押すのが基本
契約書のひな形やテンプレートには、あらかじめ「捨印欄」と書かれた空欄が用意されていることがあります。このような場合は、必ずその欄に捨印を押しましょう。位置としては、文書の右上や左上に設けられていることが多いです。
② 捨印欄がない場合:ページ上部の空白に押す
もし捨印欄が設けられていない契約書の場合は、各ページの上部余白に押すのが一般的な方法です。特にルールが厳密に定められているわけではありませんが、「捨印だと一目でわかる位置」に押すことが大切です。
契約書の文面や署名欄と混同しないように、見やすく、明確に分かる場所を選びましょう。
契約書が複数ページある場合は?
契約書が1ページだけならそのページにだけ捨印を押せば十分ですが、複数ページにわたる場合は注意が必要です。
なぜなら、どのページに訂正が生じるかはあらかじめ分からないためです。ですので、すべてのページに捨印を押しておくのが安全策となります。これにより、どのページで軽微な修正が必要になった場合でも、捨印があれば修正がスムーズに行えます。
このときのポイントは、「すべてのページに同じ位置に押す」こと。たとえば、各ページの右上の空白に統一して捨印を押しておけば、見た目も整い、確認もしやすくなります。
使用する印鑑の種類は?
捨印には、契約書に押印したのと同じ印鑑を使用するのが原則です。
たとえば、契約書本体に実印を押した場合は、捨印にも同じ実印を使うべきです。逆に、認印で契約しているなら、捨印もその認印で統一します。
異なる印鑑を使ってしまうと、「この捨印は本当に本人が押したものなのか?」という疑義が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
複数人で署名する契約書の場合
契約書に複数の当事者が署名・押印する形式の場合、それぞれの当事者が自分の捨印を押す必要があります。
たとえば、売主と買主、発注者と受注者など、両者が署名する契約書であれば、双方が自分の捨印を押しましょう。片方だけが捨印を押している場合、もう一方の同意が不明確となり、トラブルの原因になることもあります。
契約書を取り交わす際は、ぜひ捨印の意味と役割を理解し、正しい方法で押印しましょう。
捨印を押さないとどうなる?
・捨印を押すことで起きるリスクとは?
・相手に捨印を求められたらどうする?
・捨印が便利に使えるケースもある
捨印を押さないと何が起きるの?
結論から言えば、捨印を押さなかったからといって、契約書や書類の効力が無効になることはありません。法律上、契約が成立するためには、調印欄への署名・押印がなされていれば十分とされています。
つまり、捨印はあくまで“あると便利”なだけで、“必須”ではないのです。
捨印を押すことで起きるリスクとは?
一方で、捨印には注意すべき点もあります。特に重要なのが「悪用のリスク」です。
捨印を押してしまうと、書類の内容を相手側が勝手に書き換えることが可能になります。もちろん、信頼できる相手であれば問題ありませんが、誰もがそうとは限りません。
たとえば、契約金額や期間などの重要な部分が、後から無断で修正されていたとしたらどうでしょうか? それに気づいたときには既に手遅れ、というケースもあり得ます。
相手に捨印を求められたらどうする?
「この書類、念のため捨印を押してください」と言われたら、どう対応すれば良いのでしょうか?
基本的には、捨印を押す義務はありません。相手から求められたとしても、きっぱりと断ることができます。特に、「この人、ちょっと怪しいな…」「何に使われるのか不明確…」と感じた場合は、なおさら注意が必要です。
そのような場合は、「必要があれば自分で訂正しますので、今回は捨印は控えさせてください」と丁寧に伝えると良いでしょう。
捨印が便利に使えるケースもある
もちろん、捨印がまったく不要というわけではありません。相手が公的機関や信頼できる企業・専門家である場合には、書類の手戻りを防ぐために捨印が役立つこともあります。
たとえば、住所の番地が一部間違っていた場合でも、捨印があればわざわざ連絡することなく訂正して処理を進めてもらえるので、スムーズに事が運ぶというメリットがあります。
捨印に関する正しい知識を持ち、書類のやり取りでも自分の権利と安全をしっかり守っていきましょう。
捨印はどこに押す?押さないとどうなる?まとめ
記事のポイントをまとめます。
捨印とは
– 契約書などに軽微な訂正を加える際、事前に同意を示すための印鑑。重大な変更には使えない。
押す位置
– 捨印欄があればそこに、ない場合はページ上部余白へ。複数ページある場合は全ページに同じ位置で押すのが望ましい。
印鑑の種類
– 契約書と同じ印鑑を使用。異なる印鑑は本人確認に疑義が生じる。
複数人の契約書
– 各当事者がそれぞれ捨印を押す必要あり。
押さない場合の影響
– 契約自体の効力に影響はないが、訂正に手間がかかる可能性あり。
リスクと対応
– 悪用の危険もあるため、相手が不明確な場合は丁寧に断るのも一つの方法。
活用シーン
– 信頼できる相手との書類や公的機関向け文書では、処理の迅速化に役立つことも。


